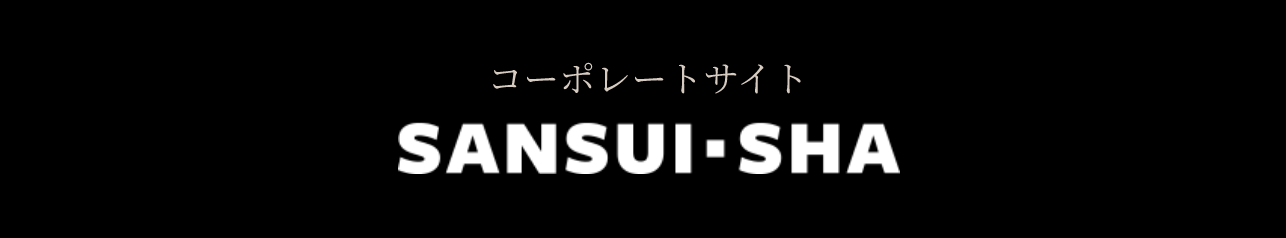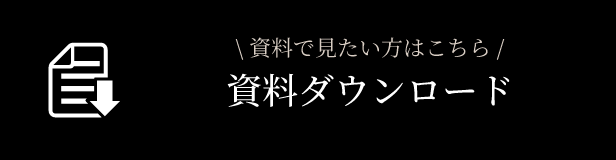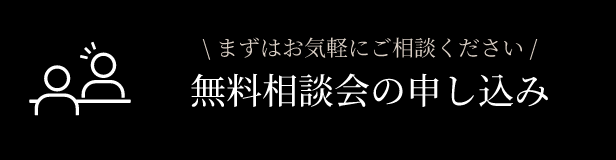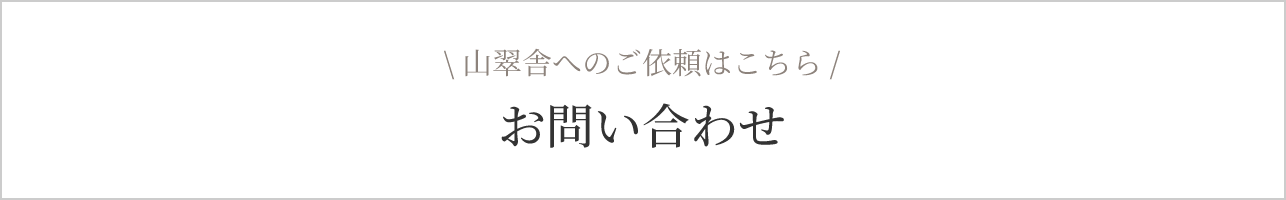2019年12月27日にオープンした「ひるあんどん」。
農家さんから直接仕入れた蕎麦の実を毎日お店の石臼で挽いてつくる手打ち蕎麦のお店です。
オーナーは和食料理人の修行を経て、蕎麦職人の道を選んだ高木知洋さん。落ち着いた空間でゆったりお酒を飲みながら、料理とお蕎麦が楽しめる。そんなお店にしたくて、立地から内装まで決めていったといいます。
オープンまでの経緯や内装にこめた考えなど、高木さんにお話を伺ってきました。
— 高木さんは和食料理の世界で修行されてたと伺ってますが、その中で、なぜ最終的には蕎麦屋さんをやろうと思われたんですか?
もともとは手に職をつけようと思いまして、和食屋さんで5〜6年ほど仕事をしてたんです。
でも和食って幅が広いので、いろんなことをやるんですね。もう少し一つのものに特化したというか、突き詰めた職人の方向に行きたくなったんです。その方向が自分には向いてるんじゃないかとも思いまして。
和食にもお寿司とか天ぷらとかいろいろあるわけですけど、やっぱり蕎麦が自分にとって身近だった、子どもの頃から食べ慣れてたっていうことと、あと単純に美味しい、自分が好きだからっていうことですね。それで蕎麦職人でいこうと思って。
— 高木さん自身が蕎麦マニアみたいなところがあると?
そうですね。
和食屋さんの時も休みの日に食べ歩きみたいなことをするんですけど、なんとなく蕎麦屋へ行くことが多かったですね。
— 今回山翠舎に内装をお願いするなかで、どんなところにこだわりましたか?
やっぱり蕎麦の打ち場をある程度確保したくて。最初の設計段階だと狭い空間だったんですけど、大きい台を入れたかったんです。
それで(デザイン設計案を)何パターンか、紆余曲折があって今のかたちになったんですけど、これだけの広さを確保してもらって正解だったなと思いますね。
あと、カウンターはどうしても作りたかったので、いいカウンターにしてもらいました。
テーブルで3〜4名様とかご家族連れとかもいいんですけど、けっこう蕎麦好きの方って一人でふらっと入ってちょっとお酒飲んでっていう方が多いので。
そういうお客さんに、カウンターでお酒と料理とお蕎麦を楽しんでほしいなと思いまして。
それでカウンターをつくったわけですけど、その場所だけはなるべく予約で埋めないようにしてます。

— そういう気さくな雰囲気と関係がある気もしますが、「ひるあんどん」というお店の名前、これにはどんな意味があるのですか?
和食時代の親方が、いわゆる昭和の親方で、毎日頭ひっぱたかれたり怒られたりしながらやってたんですけど、
そのときだいたい決まって言われてたのは、「おまえはホントにひるあんどんだな」って。
「役立たず」とか、「ホントにおまえは使えないな」っていうことなんですけど。
そんな親方が、今もすごくよくしてくれますし、面倒見てくれるんです。
だから初心を忘れないと言う意味で、自分はひるあんどんだけど頑張ろうみたいなことで、この名前にしました。
— 古木も結構な数を内装に入れてますね。
お客さんも気になるみたいで、「どこの古民家にあったものなんだ? 」とか、「どこにあった柱なんだ?」 とかよく訊かれます。
長野の松本の古民家にあったもので、柱はケヤキ、梁が松ですね。
将来は自分で開業したいな、独立したいなと、そうずっと思ってたわけですけど、
2〜3年前にテレビで山翠舎さんを特集した番組を見たときに、こうやって古木を捨てたりせず飲食店や事務所の内装に使ってる。いいなあと思いましたね。
あと、蕎麦屋って木の板と木の棒で蕎麦を打つわけで、蕎麦屋って木と相性がいいなって思ってました。
それで山翠舎さんの施工事例を見させてもらったら、
コテコテの古民家になっちゃうと水車が回ってる蕎麦屋さんみたいなイメージになっちゃうんですけど、
モダンな感じで施行されていたので、これはいいなと思いまして。それでぜひお願いしようと。

— そしてこの場所で開業されたわけですが、なぜ板橋の、少し駅から離れたこの場所を選んだのですか?
生まれ育ったのが隣の十条という街で。今現在も板橋区の大山に住んでるので、この辺には土地勘があるというか。
ここ、板橋駅と下板橋駅の間なんですけど、繁華街過ぎない、こういう住宅地の落ち着いた感じが合うなと思ったので、
この辺で物件を探してました。
— まだまだ始まったばかりで(*このインタビューはオープンから半月後の2020年1月にしています)これからお店を育てていかなきゃいけないと思うんですけど、これからこんなお店にしていきたい、っていうのはありますか?
お昼はご近所さんとか近所の事務所とか会社の方に美味しいお蕎麦を食べてもらって、
夜は少しお酒とかも召し上がってもらう。落ち着いてゆっくり飲んでもらって最後にお蕎麦を食べてっていう感じのお店を目指してます。できれば地域密着でいきたいですね。
— 今日はありがとうございました。
板橋近辺にお立ち寄りの際はぜひみなさんも、立地、空間ともに落ち着いたこの場所で、
丁寧に作られた高木さんのお蕎麦を味わってみてください。
僕も取材の後にお蕎麦をいただきました。
とても美味しかったです。