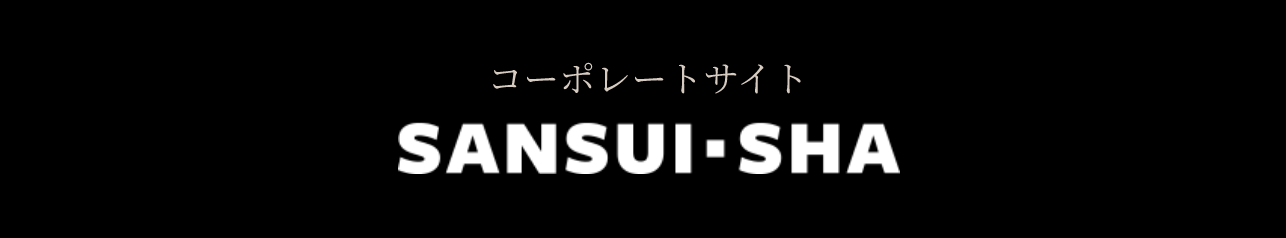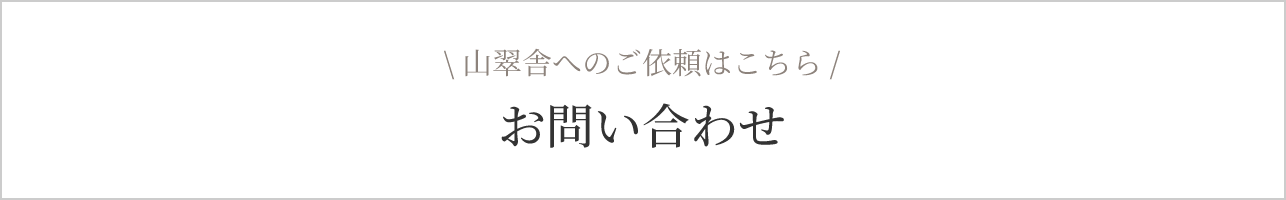東京、葛西駅の南口繁華街にある酒屋さん「平三郎商店」。バブル期は、ビール販売で賑わう地元の人気店でした。それが1990年代の中頃、突如日本酒をフィーチャーしたスタイルに舵を切り、今日まで、まちの地酒屋として日本酒ファンの支持を得ています。
そんな平三郎商店が2023年8月4日、山翠舎の施工によりリニューアルオープンしました。そこにはどんな背景があり、どんな展望を描いているのか? お店を訪ね、店舗リニューアルのディレクションを行った佐久間輝行さんに、お話を伺ってきました。
(2025年7月16日 取材)

— お店の創業はいつですか?
父親が作ったお店で、創業が何年か正確には覚えてないんですけど、昭和50年代の中ごろだったと思います。
— いわゆる町の酒屋さんみたいな感じで始まったのですか?
いえ、もともとは酒屋じゃなかったんですよ。
当時の酒販は(*需給調整という厳しい基準下での)免許制だったんです。今は許可制なので(*規制緩和で需給調整基準が廃止されたので)、やりたい人は税務署に申請して「いいですよ」ってなったらできますけど。
ここのビルのオーナーさんが父親の遠縁の親戚筋で。1Fの店舗スペースが空いていたので、「なんかやってくれないか」といわれ、商売をやることになったのが最初です。
父は酒屋をやろうと思ったらしいんですけど、許可が下りなかったので、最初の数年間は今でいう個人経営のコンビニみたいなお店を作ったんですね。
そのあと何回か申請を出して、数年後にようやく、今の立ち飲みスペースくらいの場所で酒屋になったんです。

— 最初は、この角打ちスペースの大きさの店だったんですか?
正確に言うと、もうちょっと大きかったですけど、まあ、今の店の広さの半分です。
今の広さになったのは、僕が「専門学校を卒業したら店を継ぐ」みたいな話をして、それで父が「お前がやるんだったら、空き店舗になってる隣も借りて、2軒分ぶち抜いてお店を作ろうか」と。
— そして卒業後、輝行さんが店を任されることになったわけですね。
店をやるにしても、僕自身はどこか他の酒屋で働いた経験もなく、お酒もまったく飲まないんですね。単に学校を卒業して、「はい、これからはお前ね」って丸投げされた状態。なので、ただ父親がやってたことを継承しただけ、といいますか。
当時はバブルの後半、1990年前後だったと思うんですけど、リーチイン冷蔵庫が8面あったんです。しかも、今だとコンビニにあるんですけど、後ろから物を詰められるタイプの冷蔵庫。当時、後ろから物を補充できる冷蔵庫を備えている酒屋さんはほぼほぼなくて、それが8面もあったんです。そこにほぼすべて、ビールを入れてた。酒屋で、ビールが8面にわたってブワっと並んでるような店なんて、ほかになかったんです。
—なるほど。店独自の強みですね。
そんな時期に、アサヒビールからスーパードライが発売されて。もう、超人気ですね。あまりに人気で、世間では入荷困難な状態が続くなか、うちは問屋さんが協力的だったので毎日入荷できてたんです。
今だとビール6本パックの販売って当たり前になってますけど、当時は24本バラで入荷するビールを、自分たちで手提げ式のビニール袋に6本づつ詰めて冷蔵庫に入れてたんです。そうやって6本パックで冷やして置いてあるような店がほかになかったんです。
それでうちは圧倒的な回転率を上げることになったんです。売上もかなり増え、バブル崩壊後もしばらくはその余韻は続いたんです。
それがどういうわけか、急に父親が「これからは地酒だ」って言い出したんです。
— なんと。

もう僕からすると、何を言っているのかまったくわからない状態。
そうこうするうちに地酒の問屋さんを連れてきて、「この人に地酒のことは教えてもらうから」って。そこから地酒問屋さんとの関係が始まって、だんだん店からビール売り場が削られ、お酒の売り場が増えていって。
— お父さんが「これからは地酒だ」って言い出したのは、90年代中ごろ? アサヒスーパードライのブームの後ぐらいですか?
後ぐらいですね。
僕は「何を言ってんだろう」ぐらいの感じだったので。
— なぜそう思われたのか、その動機はわかりますか?
まったくわからないですね。
仲良くしてた地元の飲食店さんで地酒しか置いていないお店もあったので、そういうところで感化されたのかもしれないですし。
何にしても、急に「これからは地酒だ」って言い出して、で「お前、やれ」ですから。
— ああ、お父さんは言い出すだけなんですね(笑)
ちょっとはやるけど、結局は「お前がやるんだから」って。
— そしてビール屋から地酒屋に変わり、今日まで酒屋として続いてきたわけですね。
そんなお店を今回リニューアルしようと思われたのには、どんな背景があったのですか?
もう、完全コロナですよね。
リニューアルの計画自体はその前から頭の片隅にはありましたけど、予算もかかるので、なかなかやりかねてたんです。
ただ、かなり年月の経ったお店なので、冷蔵庫の動力も、扉も、セラーも、いろんなところが壊れ始めていて。このまま応急処置で直しなおしやってても、これから先、すべてにお金がかかる状態になってしまう。どこかのタイミングでまとめてリニューアルしようとは考えていたんです。ただ、お金的なことを考えると、なかなか。
そんなときにコロナに入り、お客さんでコンサルタントをやられている方から、事業再構築補助金というものがあると教えてもらって。これは金額も大きい、ただ申請が通るにはちょっとハードルが高い。しかも事業再構築なので、ただお店を新しくするんじゃなくて、内容も大きく変えなければいけない。
「じゃあ、立ち飲みだな」と。ただその時点では、誰がそれを切り盛りするかも考えてなくて。コンサルの方と相談しながら、でも申請を通すためには「一応、設計をしてもらわなきゃいけないから、どうしようか?」ってなって、「うちのお客さんで、設計士の人がいるから頼んでみようか」と。
— そのデザイナー(設計士)が榊さんだったわけですね。
はい。
そもそも、「父親の代からやってきたこのお店をもし改装するなら、お酒を理解している人に設計してもらいたい」っていうのは、僕の根本の考えとしてあったんです。
コロナになって補助金の話になって、それまでうちが主催する「お酒の会」にも何回か出席してくれてる榊さんなら、お酒のこともよく知ってるし、「こういう管理がしたい」「こういう設備が必要なんです」ってことに対して、理解してくれそうだなと。
それで榊さんに話をしたら快くOKをいただいて、それで事業再構築補助金の書類を出せる条件がパッとできちゃったわけです。
それで提出して、1回目はダメでしたけど、2回目に採択されました。

— 山翠舎に内装の施工を依頼したのは、どんな経緯があったのですか?
山翠舎さんの話が出てきたのは、まず榊さんに「どこか施工業者、知ってますか?」って聞かれたので、「いや知らない」と。そしたら「山翠舎さんという施工業者さんがいますが、どうですか?」と。
実はそれ以前に、お取引しているある飲食店さんを訪ねたとき、その横にあったお店の雰囲気がいいな、と。気になってあとで調べたら、それが(山翠舎が施工した)「あぶくま亭」さんだったわけ。しかも「あぶくま亭」さんも、うちにお酒を買いに来てたお客さんだったんです。
それから、前々から知っている男の子が「お店をやるんです」って言ってきて。その彼が、西麻布の「鮨いち」の佐藤君。そこで山翠舎さんの名前をまた聞いたんです。(*「鮨いち」も山翠舎の施工)
それで気になって山翠舎さんのホームページを見て、いいなと。僕自身、宮大工が作った釘を使ってない木の家に住んでいたものだから、木というのはいいなって思っていたんだけど、まあなかなかね。予算的にできること、できないことがあるなと思いつつ。
そんなときに、榊さんから出てきたのが山翠舎さんだったから、うん、これはもう運命の巡り合わせだなぁと思って。二つ返事で「そうしましょう」と。それで山翠舎さんにお願いすることになったんです。
— 何だかドラマのような流れですね。
そしてお店が出来上がったわけですけど、こだわった場所や気に入っているポイントはありますか?
結局、僕らはずっとこの場所で商売をさせていただいていて、父親が作ったにせよ、その設備をずっと利用してきたので、新しいイメージっていうのはまったく湧かないんですよ。
お酒をどう保管するとか、管理上こうしたいっていうのはあるんですが、お酒の見せ方、こういう平台で陳列するようなイメージは僕にはなかったので。
榊さん曰く、最近はもう外から奥まで見渡せる店舗の方がいいということで。これまで棚が当たり前だった酒屋さんも、パン屋さんとか本屋さんと同じように平台陳列で目線が下にくる。今はこういう時代だっていうのは、実際作ってもらわないとわからなかったですね。

— リニューアルオープンされたのが2023年の8月。ちょうど2年ほど経ちましたが、どんな調子でしょうか?
今の僕は店頭に立ってないので、数字でしか見てないですけど、数字で言えば2年間、ほぼ上向きです。月比で考えると、だいたい25%の来店客アップです。客数で言えば15%アップ。
ただ、昨今値上げの問題が大きくて、客単価が若干伸び悩んでる感じはしますけど。今まで一升瓶を買ってたお客さんも、四合瓶に変えたりとか。
まあ客単価は前年並みぐらいで、値上がり分の伸びしろはちょっとないですけど、全体としては合格点なのかなと思っています。
— 角打ちスペースを作ったことでの変化はありましたか?
角打ちは、これで売り上げをバンバン上げようっていうイメージではなくて、店で売ってるお酒を試してもらうのが目的なんですね。
やっぱりどんだけお酒の味を説明しても、お客さんから「結局飲んでみないとわかんないよね」って言われ、話を切られることがこれまでも多々あったんですよ。
あと、一つのお酒でも、例えば常温、冷やして、温めてと、いろんな角度から見ることで顔が変わるでしょっていうのも知ってほしかったですし。
角打ちでは、「お客さんは少なくてもいいから、来た人が『へえ』って思って帰っていただけるような仕事をしてね」って、ここのスタッフには言ってるんです。今だったら夏のお酒とか、千葉県では楽天ナンバーワンの売り上げがある鶏専門店の焼き鳥をおつまみでメニューに入れたり。あとは取引している飲食店さんにお惣菜を作ってもらったり。味醂のハイボールをラインナップしたり。

— 味醂のハイボールですか。興味が惹かれますね。
お客さんが「これ飲めるの?」って。ちょっと会話が生まれるんです。「この味醂はアイスクリームにかけたら美味しいですよ」とか。そうやってお客さんと会話すると、「じゃあ1本買って帰るか」と。
試して、面白がってもらって、それが購入につながる。どんどんお客さんと情報共有することで、いろいろな可能性が生まれるスペースになるわけで。
— 先ほど「今の僕は店頭に立ってない」と言われましたが、今店頭に立ってお店をやられているのは、お母様の和子さん?
そうです。
— お店はお母様がやられているけど、今回のお店のリニューアルをディレクションされたのは、輝行さんということですね?
そうですね。
(*ちなみに輝行さんは隣の浦安市で「無銘良酒 輝酒」という酒屋をやっています)
— 今後はどんな展開をしていきたいですか? イメージされているものはありますか?
いや、もうお店を遊び場にできたらなっていうだけです。
このあいだも、キッチンカーでお寿司屋をやっている方に、ここ(角打ちスペース)でお寿司を握ってもらったんです。

— それは事前に、常連さんに「こんなことやります」みたいな告知をして?
はい、連絡して。
握り十貫と茶碗蒸しとお吸い物でいくら、という感じで。一時間半で1回転の3部制にして。結局24人ぐらい集まったのかな。
1部にいた人が2部、3部になっても帰らなくて。「もうお寿司ないよ」って言っても、お酒は飲み放題にしてたから、結局、帰らない人は仕切りの向こうで飲んでもらうっていうふうにしてやりましたけど。まあ、そういうのが楽しいですよね。
今度はお蕎麦をやろうかなと思ってるんです。浦安に蕎麦打ちをやっているお店の方がいて、女性のオーナーさんなんですけど、お蕎麦を出してるのにエスニックな一品料理が多い。その方に今度ちょっとここでやってもらおうっていう話になってて。
— まさに遊び場ですね。
遊び場です。もう完全に。
あと、かき氷もここでやりたいと思っていて。お酒を使ったかき氷。例えば台湾のかき氷って、日本みたいにマンゴーを後から氷にかけるんじゃなくて、マンゴージュースを凍らせたものをかき氷にしてるじゃないですか。じゃあ日本酒をかき氷にしたいなと思って、今いろいろ実験してるんです。でも日本酒、凍らないんですよね。
そんな感じで、今がステップ1で、ステップ3ぐらいまではビジョン的にちょっと考えているんです。
— いいですね。角打ちスペース一つで、ほんといろんな可能性が広がりますね。