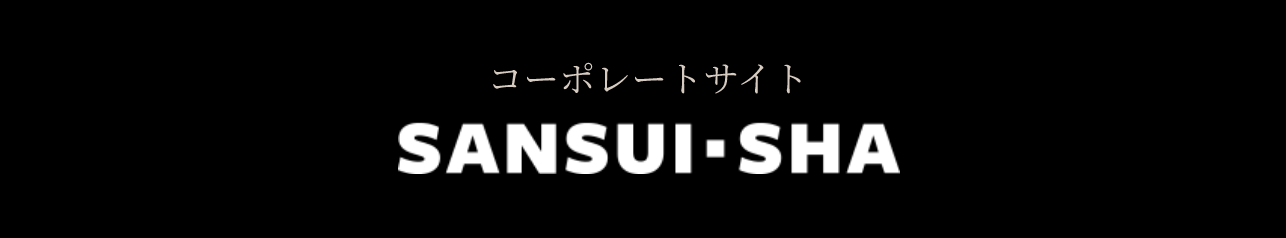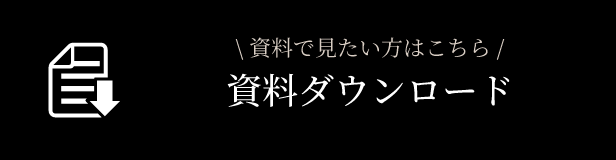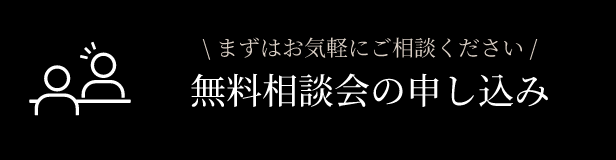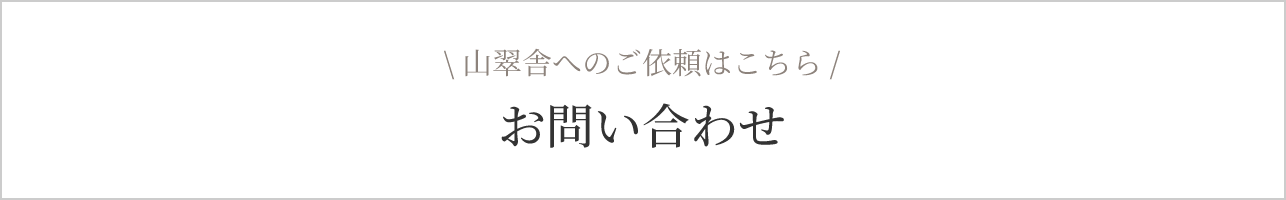東京の武蔵関にあるお蕎麦屋さん。 お父様の代から36年続いたお店を息子さんが、バックパッカーや様々な経験をした後、引き継ぎました。 地元の方がくつろげるような空間という良いところはそのままに 今まで以上にお年寄りはもちろん、外国人の方や若い方、女性が入りやすい空間になりました。 古木を使った温かい空間にした経緯や料理、雰囲への工夫や想いをお聞きしました。 ■自己紹介をお願いいたします。 古山潤一です。 ■お蕎麦屋さんをやるまでの経緯を教えてください。 親父が36年間ぐらいずっとここでお蕎麦屋さんをやってて 僕は蕎麦屋のせがれとして生まれ育ったんですけど。 まあ、子供の頃は絶対に蕎麦屋なんか継がないと思ってました。 年齢を重ねるごとに色々経験して・・・色々ちょっと好きなことやらせてもらったんですよね。 若い頃にあのバックパックとかして。 海外に行ってた時にすごい日本食が恋しくなって 食べるものがね、なんかあまり美味しい物がなかったんですよね。自分の口に合うものが。 その時に日本食がすごい恋しくなって、蕎麦も無性に食べたくなったんですよ。 向こうにいる時に日本に帰ったら何にしようかなと思った時に、 親父の店を継ぐのもいいかもしれないなと思って。 そっからちょっと意識し始めてというか、まぁ蕎麦屋を継ぐ方向に人生がシフトしていった感じです。 ■お父様の時とはお店の雰囲気が違いますね 親父がやってた頃はほんと町のお蕎麦屋さんっていう感じで。 それこそお蕎麦以外にもうどんとかラーメンとか、かつ丼とか丼ものもあるし、もう全部色々ありました。 店屋物とかあり、出前とかもやっていたんで地元の人に愛される町の蕎麦屋っていう感じでずっとやっていたんです。 ただ、僕がもし継ぐのであれば蕎麦一本に特化して本当に美味しいお蕎麦を出したいなと思って。 今までおやじは機械打ちでお蕎麦をやってたんですけど、 僕の代にする時に手打ちのお蕎麦に変えました。 お店も山翠舎さんにお願いして内装もガラッと変えてもらって。 以前は厨房と客席が完全に仕切られた感じのお店だったんですけど、 カウンターを作って、 厨房もお客さんから見えるようにオープンキッチンみたいな感じに作ってもらって お客さんとコミュニケーションをとりながら接客できるようなコンセプトで設計してもらいました。 ■海外を色々見た中で古木の空間を作るヒントなどはございましたか? 自分が結構、木目とかそういう木の素材感がすごい好きというのもあるのですが。 元々高校卒業してインテリアがすごい好きだったんでインテリアの専門学校に行ったんですけど 僕が行った先はインテリアコーディネーターを目指すような専門学校で、 学んでいくうちに、売ってるものを配置するんじゃなくて、自分で作りたいっていう風な考えが強くなって。 専門学校を卒業して、大道具の会社に勤めてCMのセットとかを主に作っていたんですけど。 その時に木材を使った加工とか、大工仕事みたいなことを仕事でやらせてもらって。 それでより一層木が好きになりました。 木のぬくもりって温かい感じがして、同じ木目というのがないという そういう個性がずっと好きではあったんで。 もし自分のお店をやる時は、木をふんだんに使った内装で作りたいなと思って。 こういう感じの木をふんだんに使った内装に仕上げてもらいました。 ■山翠舎を知ったきっかけ、選んだ理由は? 山翠舎さんは最初に知ったきっかけは、 店を改装しようって思ってインターネットで検索したんですよね。 インターネットで木をうまく使って仕上げてくれる会社を探してたら ちょうど山翠舎さんが出てきて。 山翠舎の本社が長野にあって しかも古木を使うのが得意っていうのをサイトで見て、ここだな!と思いました。 僕も蕎麦修行で長野の方にずっといたので、 長野にある会社だったらもうここしかないなと思って、すぐ決めましたね、山翠舎は。 ■古木であることはポイントでしたか? 古木もやっぱりすごい自分の中ではポイントが高いですね。 この柱一つにしても同じものがないし、木の素材感が出ていて。 うちに初めて来てくれるお客さんも、内装はすごいモダンなんだけどすごい居心地がいいって言ってくださって。 たぶんそれはモダンな中にも、 こういう古い古民家で使われた古木とかを使った内装にしてるから 昔の歴史も感じられるので、お客さんも居心地がいいと思ってくれるのかなと思いました。

■ヴィーガンに対応したメニューがありますが、 日本の伝統のお蕎麦とSDGs的な考えがどのようにして融合したか経緯を教えてください ヴィーガンの人向けに今お蕎麦を出してるんですけど。 精進せいろと、精進かけそばと、大豆ミートの豆乳だれせいろっていう、 全部ヴィーガン向けのお蕎麦なんです。 最初にヴィーガンを知ったのが僕はカナダに住んでる時なのですが。 外国人の方ってすごい食べるものを気にしていて、 添加物が入ってるものとかを避けるようにしていました。 なるべく自然の食品であんまり添加物が入ってないものを食べたり 自然にいいもの地球にいいものを取りながら共に暮らしていこうみたいなライフスタイルだったんですね。 僕の住んでたカナダのウィスラーってどこなんですけど、 皆さん自然も大事にするし、自分の体とかも大事にする方が多かったので そこからそビーガンっていうものを知りました。 お蕎麦ってすごい健康にいいんですよね。 体にいい食品なんで、海外の人にもっとお蕎麦を食べて欲しいっていうのがあって。 何か外国人の方向けにメニューを作りたいなーと思ってた時に、 ビーガンの人向けに何か作ろうかなーっていうのがきっかけです。 大豆ミートとか使って研究し始めて、 今では精進せいろとカツオとかを使わずに椎茸と昆布で出汁をとって それでお醤油とかの返しで割ったおつゆとお蕎麦って感じです。 海外に行ったからこそそういうメニューを作ろうと思ったきっかけになったと思います。 ■ヴィーガンの外国人の方は日本食の出汁がネックになって食べられない方もいらっしゃるので 日本食のお蕎麦を楽しめるということで、喜ぶ方も多いのではないですか? わざわざ遠くから「ビーガンのお蕎麦があるって聞いたので来ました」って言って来てくれる方もいたりして。 蕎麦屋さんって日本にいっぱいあるからもっとビーガンのお蕎麦とか広まれば 日本食の枠を超えて世界をでも通用する食になるんじゃないかなと思うんですけどね。 ■海外を色々見ているからできることですね。 そうかもしれないですね。 自分が経験してそういう気づきがあったので、 今までの経験がプラスになってこういうことにも繋がってきてよかったなと思います。

■長野の山翠舎だったからというお話がありましたが 長野ならではのこだわりの食材がありますか? 僕が長野で修行していたというのもあるんですけども、 それまで長野って全然僕にとっては何の縁もない地だったんです。 修行のため2年ぐらい住んだんですけど。 2年住んですごい気に入ってしまって。 長野の風土と言うか、僕が住んだのは茅野市って言っていう八ヶ岳の麓にある場所だったんですけど。 そこで蕎麦の栽培からいろいろ勉強させてもらいました。 信州風土と言うかね、それがなんか自分の中で衝撃的に良くて。 色々海外も見てきたんですけど、もし日本で住むならここに住みたいなって思ったぐらい 僕にとってはすごく居心地のいい場所でした。 うちで出してるお蕎麦は信州そばで、八ヶ岳の麓でとれたお蕎麦を使って二八そばで出しています。 あとお酒もクラフトビール、日本酒、焼酎ってあるんですけど 日本酒はもう全部信州の地酒を揃えていて、東京でもあんまり見たことがない 知名度が無いようなものもだいぶ多いので 日本酒好きのお客さんからはそうそういう見たことない銘柄を飲むのを楽しみに来てくださったりしています。 飲んでもらうと絶対「美味しい」って言ってくれます。 僕も結構自分でもしょっちゅう長野の酒蔵に行って日本酒を買わせてもらうんですけど 日本で新潟に次いで二番目に酒蔵が多い街なので、 もっと長野のお酒がみんなに知ってもらえたらなと思って うちは全部信州の地酒を置かせてもらってます。 ■お客さんにとってどういうお店でありたいですか? お客さんにとって安らげる場所になったらいいなと思っています。 練馬の武蔵関って、結構都会に勤めていて仕事で帰ってきてちょっと家に帰る前に うちで一杯飲んでいくとかお蕎麦を食べていくと言う人が結構多かったりするんです。 そういう人たちがくつろげる事を意識して空間づくりをしています。 空間作りとかお料理もそうなんですけど、 音楽もお昼はちょっとメロウな曲、あんまり騒がしくない曲をかけたり 夜はジャズとかかけて ゆっくり自分の時間を過ごせるというか。 お友達と来てもその友達との会話が、どんどん弾んでしまうような そういう空間を作りたいなっていうのはすごい意識はしてますね。 ■お勤め帰りの方だけでなくいろいろな方がいらっしゃるともお聞きしていますがいかがですか? ママさん達がきて昼間からクラフトビール飲みながら世間話していたり、お年寄りも来てくれたりしていますね。 ■地元に密着した空間ということで、いいですね。 そうですね。僕もここが地元なので やっぱ地元の人に使いやすいお店でありたいなとは常に思っています。 ■内装のこだわりポイント こだわりポイントはカウンターとオープンキッチンの感じです。 あと、この古木の柱。 予約してくれるお客さんには絶対そこの角の席を予約席で取ってるんです。 そこの角に座るとちょうど店の全体が見れるんですよね。 だから初めて来てもらうお客さんとか予約してもらった方は そこに座ってもらってあのお店の雰囲気を見てもらいながら お料理を楽しんでもらうっていう感にじはしています。

■壁のギャラリー空間の写真についてもお話いただけますか? この写真とかも飾ってあることによって 最初はね、何この写真?と思われるかもしれないんですけど 「僕がバックパックとかで旅してる時に撮った写真なんです。」って一言いうと そっから結構お客さんとの会話が盛り上がったりします。 インドとか地中海のマルタ共和国とかの写真とかが結構あるんですけど やっぱそういう国に行かれたことがあるお客さんはより一層、親近感を持ってもらえます。 あそこの国に旅行に行った時の思い出話とかをして話が盛り上がったりするんで。 この写真もね、結構話のきっかけにはすごくいい効果があるんです。(笑) ■写真自体がとても素敵ですね。自分も旅に行きたくなるような写真です。 今のご時世なかなか旅に行けないですけど、だからこういう写真を見て、ちょっと楽しんで もらえたらなーっていうのもありますね。 ■3年近く海外に行かれていたとの事ですが膨大な量の写真がありそうですね。 膨大な量の写真があったんですけど、ちょっとオーストラリアに行った時に カメラとSDカードごと盗まれてしまって。 あのデータが半分ぐらいなくなっちゃってそれがすごいショックなんですけど。 まぁパソコンにいくつか保存してたのがあったんで、それから厳選してそ飾ってるんですけど そういう悲しいエピソードもあったりしました。 ■バックパックで体験した食が反映されているメニューはありますか? 家で今「グリーンカレーせいろ」っていうの出してて。 グリーンカレーはタイの方なんですけど 僕が旅しててタイで食べたグリーンカレーの味が忘れられずに もしかしてあのグリーンカレーってお蕎麦にも合うかもしれないなと、 ある日突然思って作ったんですけど。 それが蕎麦との相性抜群で。 夏の間に出していたメニューなんですが、 「冷やしグリーンカレーせいろ」すごい人気で結構リピーターの人も多くて。 コロナの期間中にテイクアウトとかを始めたんですが、 手打ちそばってすぐ伸びてしまうのでテイクアウトには出せないんですけど その代わり、そのグリーンカレーとご飯で普通にグリーンカレーのお弁当として売り出してました。 「お蕎麦屋さんなのにグリーンカレーがあるなんて面白いね」とか結構言われるんです。 他にもオリジナルのそばの実バーニャカウダもとても人気です。 経験の中から生まれた商品なんですごく良かったと思います。 ■カレーは本場の味なんですね! 僕が思い出しながら作ったんです(笑) ■棚を自分で作ったり、そばを手打ちにしたり、料理もアイデアをとりいれたり つくるということが得意なのですね。 好奇心があるほうで、なんか全部自分でやってみたいっていうほうが強くなってしまって それであのいろんな国で遊びまわったりして。 お店持って落ち着いてはいるんですけど、手仕事にこだわりたいっていうのはちょっとあって。 自分の手で作り出した物って絶対気持ちがこもっているので。 それをやっぱお蕎麦だったら食べてくれた人に感じ取って欲しいなーっていうのもあって 機械打ちよりも手打ちそばがしたいっていう思いが強くて、 親父の代から変えてわざわざ手打ちそば屋にしました。 ■手仕事へこだわるのはすごくいいですね。 今は効率やコスパ中心になり機械で作られたのものが多いので。 生産性はすごい悪いんですけど、でも、やっぱ自分でしかできないことって言うか 自分でしか作り出せないものにすごい僕は価値があると思っています。 これからIT社会とかね、 やっぱり機械で量産型の世界になるかもしれないですけど その中でも、僕は個性を出した方が絶対面白いと思うので。 手仕事でできるのであれば、そっちの方を僕は進みたいなと思ってます。 そういう意味でも山翠舎さんと出会えたのは僕にとっても凄いプラスになりました。 色々こういう素敵な内装も作ってもらったんですごい満足しています。 ■アピールしたいことや一言 コロナ禍でなかなか外出とかできない中でも うちは東京にいながらこの信州そばを食べられたり信州の地酒を飲んでもらえたりするので 遠くには行けなくても東京の花月庵行けば ちょっと長野の気分も味わえますよっていうのはお伝えしたいですね。 ■女性一人でもお酒を飲んだり食事をしたり気楽に立ち寄れますか? 若い女性の方も結構来てくれてなかなか蕎麦屋で一杯やるって 若い人にとってはちょっと敷居が高いと思われがちなんですけど。 うちなんかは、普通に女性の人一人で来てクラフトビール飲んで締めにお蕎麦食べてもらったり 女子会みたいなものに利用してもらったり。 1回勇気を出して入ってくれた女性一人のお客さんは 結構リピートしてくれて何回もそれから来てくれるようになるので僕としてもすごい嬉しいですね。 ■コロナ禍での変化 実はオープン当初なかなかお客さんに来てもらえなくて。 来てくれるお客さんは、年配の方おじいちゃんとかおばあちゃんとかはすぐに入ってきてくれるんですけど。 若い人には入ってきづらいみたいで来てもらえなかったみたいなんです。 コロナの緊急事態宣言になってから、 ドアを全部オープンにして営業したら、「こんな内装になってたんだ!」 って若い人がいっぱい来てくれるようになって。 コロナになって新しい営業スタイルになって 逆にいろんな人に知ってもらえるきっかけにはなったなと思います。 ■ありがとうございました!